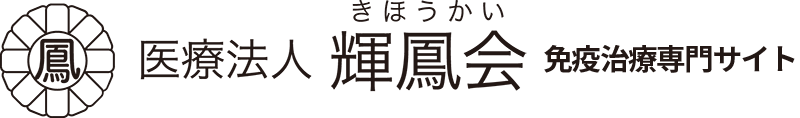副腎がん|希少がんのひとつ、治療はがんの状態や全身状態を考慮
副腎がんは希少がんのひとつとされ、一般に早期発見が難しく、進行された状態で見つかるケースの多いがんです。副腎では人間が生きるために重要なホルモンが数多くつくられているため、進行すると腫瘍が大きくなることによる身体症状のほか、ホルモン分泌異常による不調もあらわれやすくなります。
医療法人輝鳳会 理事長 池袋クリニック 院長 甲陽平
目次
副腎がんとはどんな病気か。原因、自覚症状は?
副腎がんの検査と診断
副腎がんの治療
副腎がんとはどんな病気か。原因、自覚症状は?
副腎とは、腎臓の上部(頭側)に位置している数センチ程度の小さく薄い臓器で、体のバランスに関わるホルモンを分泌しています。大きく「副腎皮質」と「副腎髄質」とに分けられますが、このうち副腎皮質から発生するがんを副腎がんといいます。
発症数は年間で390人(国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」地域がん登録2014年全国推計値による)、別の統計では100万人当たり0.72人とされており、非常にまれながんで、希少がんのひとつとされています。多くのがんは40代以降で発症ピークが見られるのに対し、副腎がんでは30~40代に多いことが特徴で、10歳未満の小児に発生することもあります。特定の遺伝性疾患がある人では、副腎皮質がんのリスクが高くなることがわかっています(リー-フラウメニ症候群、ベックウィズ-ヴィーデマン症候群、カーニー複合)。
副腎がんは一般的に進行が早く、腫瘍が大きくなるとともに周囲の臓器や組織にも浸潤していくため、進行した状態で発見されることの多いがんです。ただし近年では画像検査技術の発展により、比較的早い段階で見つかる症例が増えてきているともいわれています。おもな症状としては、腫瘍が大きくなることによる腹部や背部の張り・痛み、腹部のしこりのほか、がんにより副腎皮質ホルモンの分泌が過剰になるため、肥満や血糖値の上昇、高血圧、筋力の低下などがあらわれることもあります。副腎がんと診断された人の約60%にホルモンの過剰分泌によるこれらの症状がみられるとされ、受診のおもな理由になっています。
なお、副腎髄質から発生する腫瘍には悪性褐色細胞腫、神経芽腫、神経節芽腫などがあります。
副腎でつくられるホルモン
皮質ではアルドステロン、コルチゾール、副腎男性ホルモンが、髄質では交感神経ホルモンであるカテコラミン(アドレナリンまたはエピネフリン、ノルアドレナリンまたはノルエピネフリン)がつくられます。
●アルドステロン:体内の水分や塩分の調節、血圧の調節をするホルモンです。血液中のカリウムを減らす作用もあります。
●コルチゾール:血圧の上昇、血液中の糖や脂肪分を増やす働きがあります。ストレスを受けると血中濃度が高まるため、「ストレスホルモン」とも呼ばれています。
●副腎男性ホルモン(アンドロゲン):いわゆる男性ホルモンで、精子の形成などに関わります。男性ホルモンの95%は精巣でつくられますが、5%ほどは副腎皮質でつくられます。
●カテコラミン:いずれも血圧や脈拍を調節するホルモンです。
ホルモンは人間が生きていくために重要な働きをしているため、がんによって分泌異常が起こるとさまざまな症状があらわれやすくなります。
副腎がんの検査と診断
副腎がんが疑われる場合には、血液検査や尿検査で体内に分泌されているホルモン濃度などから、副腎皮質ホルモンに異常がないかを調べます。
また、治療計画を立てるにあたっては病気の広がりや他の臓器、組織への浸潤の有無、手術で腫瘍をとりきれるかどうか、腫瘍の性質(悪性度)などを総合的に調べる必要があります。これらは予後にも影響します。
治療の選択にあたって考慮される要素
- 腫瘍の大きさ、浸潤や転移の有無とその範囲
- 手術によって腫瘍を完全に取り除くことができるかどうか
- 過去に治療されたがんかどうか
- 患者さんの健康状態
- 腫瘍細胞の悪性度
病気の広がりなどを調べるにはCTやMRIなどが用いられます。また、腫瘍の悪性度は、細胞を顕微鏡で見て、正常な細胞との違いから判断されます。
副腎がんの病期(ステージ)は腫瘍の大きさや広がり方、転移の有無などから次のように分類されています。
| Ⅰ期 | 大きさが5cm以下の腫瘍が副腎の内部にのみ認められます。 |
|---|---|
| Ⅱ期 | 大きさが5cmを超える腫瘍が副腎の内部にのみ認められます。 |
| Ⅲ期 | 腫瘍の大きさはさまざまで、以下の領域に拡がっています。 周辺のリンパ節または周辺の組織や臓器(腎臓、横隔膜、膵臓、脾臓、肝臓) または大血管(腎静脈または大静脈)。 さらに周辺のリンパ節に転移している場合もある。 |
| Ⅳ期 | 腫瘍の大きさはさまざまであり、周辺のリンパ節に転移していることがあり、肺、骨、腹膜など、体の他の部位に転移しています。 |
なお、副腎がんの5年全生存率は海外の研究論文によれば約38~46%とされています。
副腎がんの治療
副腎がんの治療は成人の場合、手術、放射線療法、化学療法、内分泌療法があり、がんのステージや患者さんの全身状態などを考慮し、治療計画が立てられます。他臓器などへの遠隔転移がなく、病巣が、切除で完全に取り去ることが可能な範囲の場合は、まず手術が検討されます。がんが進行しており手術で取り去ることができない場合や、他の臓器に転移している場合には、薬物療法で進行を抑えることが試みられます。放射線療法は外から放射線を照射しがん細胞の死滅をはかるもので、病状によって効果があると判断された場合に行われます。
なお、内分泌療法は病気の進行を抑えることを目的とし、ミトタンという、副腎皮質ホルモンの合成を抑える薬が用いられ、おもに抗がん剤との併用で投与されます。ただし嘔吐や眠気、元気がなくなるなどの副作用も報告されており、その出方は人によって違いますので、様子をみながら慎重に投与する必要があります。
小児の副腎がんに対しても、外科的な手術による切除が治療の中心となりますが、個々のケースを検討し治療計画が立てられます。
まとめ
副腎がんの治療は手術、放射線療法、化学療法(抗がん剤)、内分泌療法(ホルモン剤)などの組み合わせで、がんの状態や患者さんの全身状態を考慮し、計画が立てられます。ホルモン剤の投与は副作用も報告されているので、慎重な投与が必要とされます。小児の副腎がんではより個々のケースを熟考した上での治療が検討されます。
| 【甲 陽平(かぶと・ようへい)】 医療法人輝鳳会 池袋クリニック 院長 1997年、京都府立医科大学医学部卒業。2010年、池袋がんクリニック(現 池袋クリニック)開院。 「あきらめないがん治療」をテーマに、種々の免疫細胞療法を主軸とし、その他の最先端のがん治療も取り入れた複合免疫治療を行う。 池袋クリニック、新大阪クリニックの2院において、標準治療では治療が難しい患者に対して、高活性化NK細胞療法を中心にした治療を行い、その実績は5,000例を超える。 |