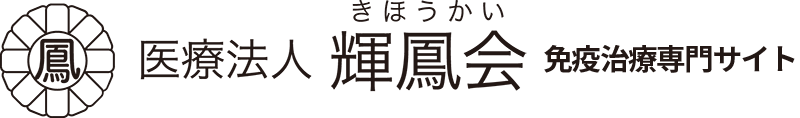三大療法が効かなければ、 がんにはもう打つ手はないのか[1−1]

こちらのコラムは書籍 『高活性化NK細胞で狙い撃つ 究極のがん治療』より、一部抜粋してご紹介いたします。
本書は免疫細胞療法の中で、がんへの高い攻撃力を期待されている「高活性化NK細胞療法」と複合免疫療法を中心に、これからのがん治療とその効果について紹介しています。
目次
現代のがん三大療法が抱える限界
手術は目に見えるがんしか対処できない
放射線治療で転移がんは殺せない
現代のがん三大療法が抱える限界
現在、一般に病院で行われているがんの治療法は、「手術」「放射線」「抗がん剤」が三本柱となっており、「がんの三大療法」と呼ばれています。それぞれ単独で行われることもあれば、病状によって手術と抗がん剤、放射線と抗がん剤といったように、組み合わせて行われることもあります。
よく「手術でがんを切ってしまえば治る」とか、「抗がん剤が効けば治る」といった声が聞かれますが、がんの治療はそう一筋縄にはいきません。医学の進歩とともにがんの治療法もここ数十年の間に目覚ましい発展を遂げていますが、手術、放射線、抗がん剤のいずれも、残念ながらこれで100%がんが治癒する〝伝家の宝刀〞にはならないのです。
もちろん医療機関で保険診療にて行われている三大療法は、臨床試験を経てがんの治療効果が科学的に認められているからこそ行われている治療法です。しかしその一方で、これ以上は効果が見込めない、ここまではできないといった「限界」も、それぞれの療法に存在します。
また、がんにおいては治療の副作用や薬剤の耐性の問題も看過できません。がんに限らず病気の治療には多かれ少なかれデメリットがともないますが、がん治療では特に副作用が大きく、患者さん自身の病気に対する抵抗力が奪われやすいのが問題です。抵抗力が落ちれば体内でがんを抑え込む力も低下し、がんが増えやすくなる環境をつくりやすいという面があり厄介なのです。また、がん以外の病気や合併症を起こすリスクも高くなります。
まずは現在、医療機関でスタンダードながん治療として行われている三大療法について説明します。
手術は目に見えるがんしか対処できない
がんの三大療法のうち、ほとんどの場合でまず検討されるのが手術です。
手術は目に見える、あるいは画像検査で確認できるがんをなくすという点では、有効な治療法です。しかし裏を返せば、目に見えないがんまでなくすことはできません。
「目に見えないがん」とは何か不思議に思う方もいるかも知れませんが、がんはそもそも目に見えないがん細胞が集まったものです。一般的に、たった1㎝のがんでも、それをつくっているがん細胞の数は実に10億個ともいわれています。
これらがじっと固まったままでいるならそこを切除すればいいわけですが、がん細胞は分裂を繰り返し周囲の組織を壊しながら広がっていきます。これを「浸潤」といいます。また、血液やリンパにのって全身をめぐり、別の臓器にたどり着いてそこでも増殖するようになることを「転移」といいます。そうした細胞一つひとつまでは、手術で取り去ることはできないというわけです。
手術を受けた後に「成功しました。がんはすべて取り除きました」と執刀医から言われれば誰でもほっとするものですが、実際は「すべて取り除いた=がんはもう体に残っていない」という意味ではありません。あくまでも「目に見える範囲のがんはなくせた」という意味なのです。
手術で目に見える病巣と転移の恐れがある周囲のリンパ節をすべて切除、他の臓器への転移が見つからなかった場合を「治癒切除」といいます。手術ではこの治癒切除が目標となります。
しかし、治癒切除ができてもがんが治癒したわけではないのです。よほどの早期でない限り、「目に見えない」がんが病巣を離れて体内を移動している可能性があるからです。本当に治癒したかどうかは、最低でも5年は経過を見て再発がなかったことを確認した後でなければわかりません。
たとえ小さくても肉眼で見える大きさであれば、すでに目に見えないがん細胞が血液やリンパの流れにのり体のどこかに潜んでいる可能性があります。
手術だけで完治するのは、ごく早期かつ局所(その場所にしかない)というたいへん限られたケースです。手術が可能な場合、術後に再発予防の目的で放射線や抗がん剤といった別の治療を行うのがスタンダードになっています。
手術が可能と言いましたが、実際のがん治療では、そもそも手術自体が行えないこともあります。がんがとても大きい場合や、広い範囲に転移してしまい原発巣だけ切除しても治療が望めない場合、患者さんの全身状態が思わしくなく、体が手術に耐えられないと判断される場合などがそれに該当します。
手術が行えないケースでは、放射線や抗がん剤などの他の治療法が検討されます。がんが大きくて手術が難しい場合は、術前に抗がん剤治療を行い小さくしてから手術を行う方法もあります。
放射線治療で転移がんは殺せない
放射線治療も手術と同様、基本的に「目に見える」がんに対するものです。体にメスを入れないので、痛みも出血もない点では体への負担は少ないといえます。
がんの治療は原則としてまず手術が検討されますが、患者さんに手術に耐えられる体力がないと判断された場合や、進行して手術が難しい場合は、放射線治療や抗がん剤治療が検討されます。放射線治療は1回の治療時間が短く、通院で受けられる点で手術と比べれば負担は少ないといえるでしょう。
しかし、負担が少ないとはいえ治療で用いる放射線は、がん細胞を変性させ殺傷するほど強いエネルギーを持った光線です。そのため、患部周辺の正常細胞にもダメージを与えます。
ただダメージからの回復は、がん細胞よりも正常細胞の方が早いことがわかっていますので、放射線治療は原則として少ない線量の放射線を何回かに分けて照射することで、正常細胞へのダメージの蓄積を避けながら、がん細胞には確実に大きなダメージを与えるという戦略をとります。
もちろんむやみに正常な細胞にダメージを与えることのないよう、照射部位は慎重に決められます。また1回の治療につき照射する線量には上限があるほか、全期間で照射する放射線の総量(耐用線量)も決められています。
そのため、病巣が1カ所ならそこだけに狙いを定めて集中的に照射できますが、あちらこちらにあると1カ所当たりの線量がおのずと限られてしまい、十分に治療しきれないということも起こります。
したがって、放射線治療は照射範囲が狭いがんにより適しているといえます。近年は治療機器の進歩もあり、ピンポイントで照射したり、複雑な形をした病巣に対してもその形に合わせて照射したりなどの、精度の高い治療法も広まりつつあります。しかしまだ、どこにいても受けられるというほどまでは普及していないのが現状です。
また病巣が1カ所で範囲も狭く、放射線を集中的に照射したとしてもがん細胞を完璧に殺傷できるとまではいえません。ダメージを受けても生き残ったがん細胞が時間とともに再び増殖し、大きくなってくる場合もあります。
がん種によっても放射線の効きやすさには違いがあります。白血病や悪性リンパ腫などいくつかのがんは放射線が効きやすいことがわかっている一方、胃がんや大腸がんなど効きにくいとされるがんもあります。
そして放射線治療にも程度に個人差はあれ、副作用の問題はあります。抗がん剤の場合は副作用の出る範囲が全身にわたるのに対し、放射線ではおもに照射した部位とその周辺にあらわれます。
放射線の副作用には「照射後短期間で出るもの(急性期)」と「照射後しばらく経ってから出るもの(晩期)」の二つに分けることができます。それぞれ、照射する部位によって出る可能性のある副作用も違いますが、ここでは代表的なものを挙げます。
短期間で出るおもな副作用としては、まず皮膚症状が挙げられます。被曝のリスクを最小限に抑えるとはいえ、皮膚を通って照射されるので皮膚の変色やひきつれ、脱毛などがあらわれやすくなります。
また、おもに腹部への照射では胃や腸管の粘膜が荒れるため、食欲不振や吐き気、下痢が起こることがあります。口の中や喉に照射すると、口内のかわきや口内炎ができやすくなります。
照射後しばらく経ってからあらわれるおもな副作用には、消化管の出血があります。これは一時的な食欲不振や吐き気とは別に、腸管の粘膜に傷がつき、潰瘍となってなかなか修復されないことで起こる可能性が高くなるものです。急性期の副作用が、時間の経過とともに回復するのに対し、こうした晩期の副作用は、回復に時間がかかる傾向があります。
また、治療後数年経ってから放射線治療を行った場所にがんが発生する「放射線発がん」も起こる可能性があります。これらの晩期の副作用はみなに起こるものではありませんが、治療後数年にわたり経過観察を行う必要があります。
このように、放射線治療にも得意不得意があり、万能とはいえません。放射線での治療効果が十分得られない場合は、抗がん剤などのほかの治療法も検討されます。