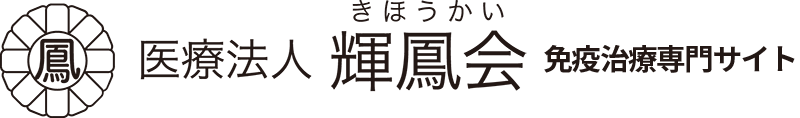抗がん剤治療は副作用が避けられない[1−2]

こちらのコラムは書籍 『高活性化NK細胞で狙い撃つ 究極のがん治療』より、一部抜粋してご紹介いたします。
本書は免疫細胞療法の中で、がんへの高い攻撃力を期待されている「高活性化NK細胞療法」と複合免疫療法を中心に、これからのがん治療とその効果について紹介しています。
目次
抗がん剤治療は副作用が避けられない
抗がん剤治療は副作用が避けられない
全身をターゲットにするので「全身治療」といいます。
現在がんの全身治療のうち、健康保険の適用内で行われる治療法は抗がん剤しかありません。しかし、よく知られているように抗がん剤の多くは「もろ刃の剣」の性質を持ち、強い副作用をともないます。
抗がん剤はがん細胞が正常な細胞よりも分裂スピードが速いという特徴を利用し、増殖の速い細胞を殺すようにつくられています。しかし、正常細胞の中にもがん細胞と同等、またはそれより速いスピードで分裂するものがいくつもあります。
例えば、毛根の細胞や消化器官の細胞などです。そのため、抗がん剤治療が行われると脱毛したり吐き気が起こったり、食欲不振になったりといった副作用が起こりやすいのです。
これらは近年、症状を緩和する薬を併用することで多少コントロールができるようになってきました。しかし、抗がん剤の副作用には長期間にわたる治療により、自覚症状が乏しいうちに進んでしまうものもあります。気づいたときには、体に取り返しのつかないダメージが及んでいることもあるので注意が必要です。
抗がん剤の副作用で代表的なものには、「骨髄抑制」「間質性肺炎」「肝機能/腎機能の低下」が挙げられます。
一般的に、抗がん剤の副作用は脱毛や吐き気がイメージされがちですが、こちらの方が深刻です。
骨髄抑制はほとんどの抗がん剤で見られる副作用です。先ほど抗がん剤は細胞分裂のスピードが速い細胞に作用すると説明しましたが、骨髄の中にあり血液をつくる役割を持つ造血細胞も増殖が活発なため、正常細胞でありながら抗がん剤の影響をとても受けやすいのです。
造血細胞が抗がん剤のダメージを受けると、血液をつくる働きが低下し、白血球が減少して感染症を起こしやすくなったり、血液を凝固させる血小板も少なくなるため出血しやすくなったりします。あざや鼻血、歯ぐきからの出血が起こりやすくなるほか、腸などの消化管からの出血で血便が出ることもあります。
一般的に抗がん剤の治療は1〜2回では終わらず、数回を1クールとし繰り返し行われるため、骨髄が回復する能力が衰え、著しい骨髄抑制を起こす恐れもあります。後でも述べますが白血球は体の免疫を担いますから、骨髄抑制により免疫力が大きく低下してしまうと、体が抗がん剤の持つ細胞毒性に耐えられなくなり治療の継続が難しくなります。
間質性肺炎は、肺の間質と呼ばれる部分にできる肺炎です。肺は肺胞という小さな袋が集まってできており、一般的に肺炎とはその袋の中が炎症を起こす病気ですが、間質性肺炎は袋の中ではなく袋の壁に炎症が起こります。
抗がん剤治療が間質性肺炎を引き起こす詳しいメカニズムは明らかになっていませんが、薬剤が気道や肺胞に及ぼすダメージや、免疫系のバランスが崩れることなどが考えられています。
また、放射線治療でも間質性肺炎を起こす場合があります。間質性肺炎になると酸素を体内に取り込む機能が低下するため、悪化すると呼吸困難に陥る恐れもあります。治療には長期間を要し、程度によっては命に関わるため間質性肺炎はもっとも避けたい副作用の一つといえます。
肝機能や腎機能の低下も注意すべき副作用です。抗がん剤は薬物を代謝する肝臓や、最終的に不要物を濾過し排出する腎臓にも負担をかけてしまいます。そのため、肝機能や腎機能低下が起こりやすくなります。著しく低下してしまった場合、抗がん剤の解毒が滞り全身状態が悪化してしまいますので、治療が続けられなくなってしまうことがあります。
たとえ副作用があったとしても、治療を受けることでがんが治癒するのならいっときの我慢と患者さんも納得できるでしょう。しかし残念ながら、悪性リンパ腫や白血病などのごく一部のがんを除き、抗がん剤でがんの治癒は期待できないのが現状です。
「この抗がん剤はよく効きます」と聞けば、これでがんが治癒する、と期待する人もいるでしょう。しかし「よく効く=治癒する」ではありません。
確かに治療で使われる抗がん剤はすべて、大規模な臨床試験を経て「有効性」が確認されています。
しかしその判定基準は、治療後にCTなどの画像診断を行い、腫瘍が一定以上小さくなった場合であり、完全に治った場合ではありません。治療後の検査でがんが非常に小さくなり、よく効いたように見えても時間とともにまた大きくなってくることもあります。それでも治療直後は、顕著に効いたように見えるため、「よく効いた」といわれるわけです。
抗がん剤でがんが完全に治るということもないわけではありません。しかし通常「がんは治癒しないが寿命が延びる」、あるいは「寿命は延びないが、がんが小さくなることで苦痛が減る」といった効果をもって「抗がん剤が効く」と表現しているのです。もちろんこれらの効果もないよりはある方が良いのですが、「治癒」とは程遠い状態であることは明らかです。
もう一つ「奏効率」という言葉もよく見聞きするのではと思います。例えば「この抗がん剤の奏効率は30%」と聞くと、体の中のがん細胞を3割減らすことができる、と受け取る人もいるのではないでしょうか。
しかしこの意味は「がん細胞が3割死ぬ」でも「受けた人の3割が治る」でもありません。「臨床試験を行った結果、有効な症例が3割あった」という意味なのです。こちらも治癒とはかけはなれています。
抗がん剤が効いてがんが小さくなり、その状態が長期間続くのであれば治癒にまで至らないとしても、その治療は有効であるといってもいいかも知れません。しかし、実際には抗がん剤治療が終わってしばらくすると、生き残ったがん細胞が再び増殖しはじめます。治療終了後に半年程度で、治療前よりも大きくなってしまうということも少なくありません。抗がん剤がよく効いて、がんの大きさが半分になったとしても、その状態が維持される期間は期待するほど長くはないのが現状です。
そして今までご説明してきた「有効」であれ「奏効率」であれ、そこには患者さんの生活の質は反映されていません。強い副作用で動くこともままならなかったり、食事がとれなかったり、ぐっすり眠れなかったりしても、がんが一定の条件で縮小していれば「有効」であり、「奏効率が高い」とされるのです。